「こざとへんに卓」って、なんて読むの? と思ったことはありませんか。
実はこの漢字、「悼(とう/いたむ)」と読みますが、部首は「こざとへん」ではなく「りっしんべん(忄)」なんです。
「悼」は、人の死を悲しむ、心を痛めるといった意味を持つ漢字で、感情を表す漢字のひとつです。
この記事では、「悼」の正しい読み方や成り立ち、似た形の「こざとへん」との違いをやさしく整理しました。
さらに、実際の使い方や覚え方のコツも紹介しているので、漢字を勉強中の学生にもぴったりです。
「こざとへんに卓」と間違えやすいポイントをしっかり理解して、漢字の構造からスッキリ覚えていきましょう。
こざとへんに卓の漢字「悼」とは?
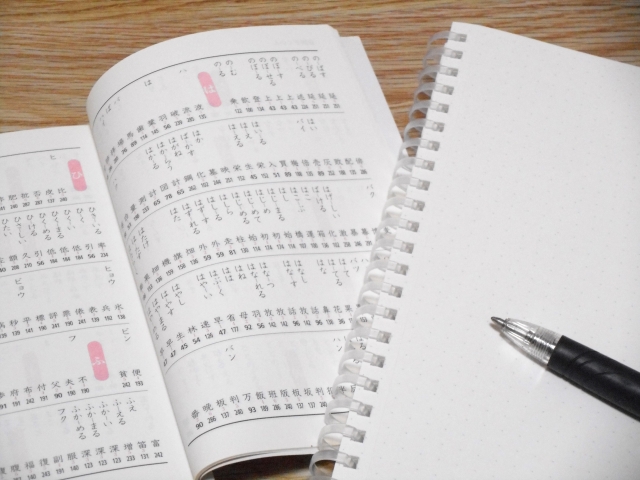
この記事の最初では、メインテーマである「こざとへんに卓」と書かれる漢字「悼(とう/いたむ)」について、読み方や意味を丁寧に解説していきます。
この漢字は一見すると「こざとへん」が使われているように見えますが、実際には「りっしんべん(忄)」が部首です。
つまり、「悼」は心に関係する意味を持つ漢字なのです。
「悼」の基本情報(読み方・音訓・部首)
まずは、「悼」の基本情報を確認しておきましょう。
| 漢字 | 悼 |
|---|---|
| 部首 | りっしんべん(忄) |
| 音読み | とう |
| 訓読み | いた(む) |
| 意味 | 人の死を悲しむ・気の毒に思う・心をいためる |
| 学習レベル | 中学校で習う常用漢字 |
音読みの「とう」は、他の熟語でもよく使われる読み方です。
訓読みの「いたむ」は、「人の死を悼む」のように日常的な表現として使われています。
「悼」の成り立ちと意味をやさしく解説
「悼」は、「りっしんべん」と音符の「卓(たかくあがる)」からできています。
心(りっしんべん)が高く動く、つまり心が強く揺れ動く悲しみの感情を表しているのです。
このことから、「悼」は人の死を悲しむ・心を痛める・あわれむといった意味を持つようになりました。
ちなみに「卓」は「すぐれて高い」という意味があり、そこから「感情が高ぶる」というイメージを持つと覚えやすいですね。
「悼」を使った言葉と例文
「悼」を使う言葉には、次のようなものがあります。
| 熟語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 哀悼(あいとう) | 人の死を悲しみ、心からいたむこと | 亡くなった友人に哀悼の意を表する。 |
| 追悼(ついとう) | 死者をしのび、思い出して悲しむこと | 戦没者を追悼する式典が行われた。 |
| 痛悼(つうとう) | 深く悲しむこと | 著名な作家の訃報に接し、痛悼の念を禁じ得ない。 |
どの熟語にも共通しているのは、「悲しみ」「いたむ」という感情です。
このように、「悼」は心の痛みや悲しみを表す漢字として使われています。
悲しい出来事を言葉で表すときに、この漢字がよく登場するのも納得ですね。
こざとへんに見えるけど実は違う?「悼」の部首の正体
ここでは、「こざとへん」と「りっしんべん」の違いをわかりやすく整理します。
見た目が似ているため混乱しやすいですが、部首の意味を理解すれば一瞬で見分けられるようになります。
また、形の似た漢字をグループで覚えることで記憶にも残りやすくなります。
「りっしんべん」と「こざとへん」の見分け方
まずは、2つの部首の形と意味を比較してみましょう。
| 部首 | 形 | 意味 | 代表的な漢字 |
|---|---|---|---|
| りっしんべん(忄) | 点が3つで縦に細い形 | 心・感情・精神に関する意味 | 悩・情・悲・快・悼 |
| こざとへん(阝・左側) | 下が丸く伸びた形 | 丘・地形・場所などに関する意味 | 防・阪・陸・院・際 |
ポイントは、「こざとへん」は土や地形を表すのに対し、「りっしんべん」は心の動きを表すという点です。
形が似ているからといって意味まで同じではありません。
似ている漢字一覧で覚えよう(例:陸・院・悼など)
次に、こざとへんとりっしんべんが混同されやすい漢字を表で整理しておきましょう。
| こざとへんの漢字 | 意味 | 似ているりっしんべんの漢字 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 陸 | おか・地面・陸地 | 悩 | なやむ・心が苦しむ |
| 院 | 建物・囲われた場所 | 情 | なさけ・心の動き |
| 際 | さかい・へり・きわ | 悼 | いたむ・悲しむ |
このように並べてみると、形の違いが一目でわかります。
見た目は似ていても、意味の分野が「心」と「土地」でまったく異なるのが面白いですね。
部首を意識した漢字学習のコツ
漢字を覚えるときは、形ではなく「部首の意味」を意識するのが効果的です。
たとえば、「悼」はりっしんべんなので「心の動き」を表す仲間として、「情」「思」「悲」などと一緒に覚えると関連づけしやすくなります。
反対に、「こざとへん」の漢字は「場所・地形」のグループとして「陸」「防」「阪」などとセットで覚えましょう。
形の似た部首も、意味をグループ化して理解すると記憶の整理が格段にしやすくなります。
こざとへんを含む漢字たちの世界
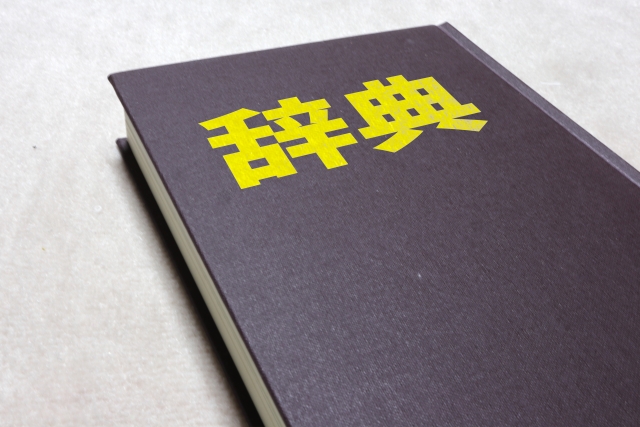
ここからは、「こざとへん」が使われているさまざまな漢字を見ていきましょう。
「こざとへん」は見た目の通り、土地・坂・丘・場所などの意味を持つ部首です。
この章では、いくつか代表的な漢字を取り上げて、それぞれの読み方や成り立ち、意味を比較していきます。
「附(ふ)」や「阳(よう)」などのこざとへん漢字を比較
まず、「こざとへん」を使う代表的な漢字「附(ふ)」と「阳(よう)」を見てみましょう。
| 漢字 | 読み方 | 意味 | 成り立ち |
|---|---|---|---|
| 附 | 音読み:ふ/ぶ 訓読み:つ(く)、つ(ける) |
くっつく・したがう・たのむ | 阝+付(手で物を与える形)で、「近くに寄る」「付ける」の意味 |
| 阳 | 音読み:よう 訓読み:ひ、ひなた |
太陽の光・ひなた・明るいところ | 阝+日。「丘の上に日が当たる場所」から「ひなた・明るい場所」を表す |
「こざとへん」は、どちらも“地形や場所”を連想させる漢字に多く使われていることが分かります。
つまり、「こざとへん」は場所の位置関係や空間的なつながりを表す部首だと考えると覚えやすいですね。
「阡(せん)」など難読漢字も覚え方を工夫しよう
次に、少し難しい漢字「阡(せん)」を見てみましょう。
「阡」はあまり日常では使われませんが、漢字検定などでは頻出の一文字です。
| 漢字 | 読み方 | 意味 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 阡 | 音読み:せん 訓読み:あぜみち・はかみち |
田の間を通る小道・墓への道 | 阝+千。「丘の中を多くの道が通る」ことから、「あぜみち」を表す |
「阡」の覚え方は、“千本の小道が通る丘”とイメージすると記憶に残りやすいです。
また、東西に通じる道は「陌(はく)」と書くので、方向の違いで区別されているのも面白いですね。
表で整理!こざとへん漢字の意味と読みまとめ
ここまでの内容を一度表で整理しておきましょう。
| 漢字 | 音読み | 訓読み | 主な意味 |
|---|---|---|---|
| 附 | ふ・ぶ | つく・つける | くっつく・従う・寄り添う |
| 阳 | よう | ひ・ひなた | 太陽・明るい・表面 |
| 阡 | せん | あぜみち・はかみち | 田の間の小道・墓道 |
このように、こざとへんの漢字は地形や場所、空間に関する意味を中心に構成されています。
“場所を示す漢字はこざとへん”という感覚で覚えると、自然にほかの漢字にも応用できるようになります。
「悼」の使い方を例文でマスター
ここでは、「悼」という漢字を実際にどう使うのかを例文で確認していきましょう。
辞書的な意味だけでなく、文章の中でどのように登場するのかを知ることで、自然に使い方を身につけることができます。
文学作品やニュースの中でもよく使われる漢字なので、読み方だけでなく使い方にも慣れておくと安心です。
「悼む」という言葉の使い方
「悼む(いたむ)」という言葉は、基本的に人の死を悲しむときに使われます。
つまり「亡くなった人を思って悲しむ・気の毒に思う」という意味です。
日常会話よりも、ややフォーマルな文面や式典などで使われる表現です。
| 使い方 | 例文 |
|---|---|
| 動詞「悼む」 | 彼は亡くなった恩師を深く悼んだ。 |
| 形容動詞「悼ましい」 | 事故で亡くなった方々のことを思うと、悼ましい気持ちになる。 |
このように、感情を静かに表すときに使われるのが「悼む」です。
感情が爆発する「悲しむ」よりも、心の奥でしずかに痛みを感じるような響きがあります。
ニュースや文学での「悼」の使われ方
「悼」はニュースや報道記事、そして文学作品などでよく登場します。
たとえば、追悼式(ついとうしき)や哀悼の意(あいとうのい)など、社会的に人を偲ぶ表現にも頻繁に使われます。
| 言葉 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|
| 哀悼(あいとう) | 死者を悲しみ、心からいたむこと | 犠牲者に哀悼の意を表します。 |
| 追悼(ついとう) | 亡くなった人を思い出して悲しむこと | 戦没者追悼の日が設けられている。 |
| 痛悼(つうとう) | 深くいたみ悲しむこと | その突然の別れに痛悼の念を禁じ得ない。 |
どの表現も、相手の死や悲しみに対して敬意をこめて使うという共通点があります。
「悼」は単なる悲しみではなく、「敬意と祈りを込めた悲しみ」を意味しているのです。
同じ読み・意味をもつ他の漢字との違い
最後に、「いたむ」と読む他の漢字との違いを見ておきましょう。
| 漢字 | 読み方 | 意味 | 使い分けのポイント |
|---|---|---|---|
| 悼 | いた(む) | 人の死を悲しむ | 心の痛み・敬意を伴う悲しみ |
| 痛 | いた(む) | 身体が痛い・苦しい | 体の痛みを表すとき |
| 傷 | いた(む) | 物理的な傷・ダメージ | 物や体の表面が傷つくとき |
同じ「いたむ」でも、使う場面がまったく異なるのが分かります。
「悼」は心の痛みを表す漢字であり、精神的・情緒的な場面でのみ使用されます。
こうした違いを意識して使い分けることで、より正確で豊かな表現ができるようになります。
漢字学習に役立つコツと暗記法
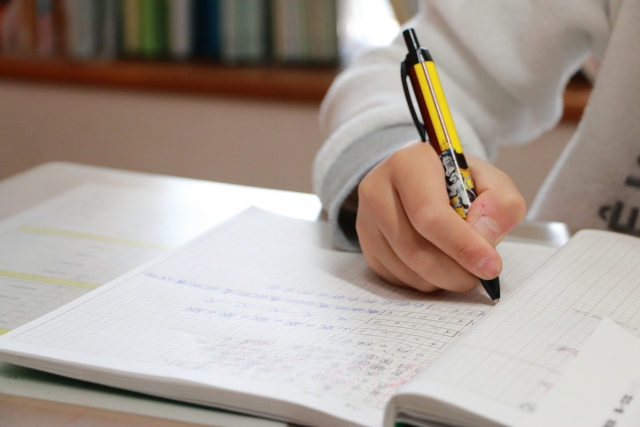
ここでは、「悼」や「こざとへん」のような形の似た漢字を効率よく覚えるための学習法を紹介します。
漢字は数が多いですが、パターンをつかめば暗記の負担を大幅に減らすことができます。
特に学生の方は、テスト対策や漢字検定の勉強にも役立つ内容です。
形の似た部首で覚える「ビジュアル連想法」
まずおすすめなのが、漢字の形をイメージで覚える方法です。
たとえば、「りっしんべん」は人の心の動きを、「こざとへん」は丘や坂などの地形を表しています。
このように、部首そのものを“意味のかたまり”として覚えると、初めて見る漢字の意味も推測できるようになります。
| 部首 | イメージ | 代表例 |
|---|---|---|
| りっしんべん(忄) | 心・感情・気持ち | 情、悩、悲、快、悼 |
| こざとへん(阝・左) | 丘・土地・坂・場所 | 陸、防、阪、院、附 |
似た形の漢字をグループでまとめて、視覚的に整理していくと混乱しにくくなります。
ノートに「部首別マップ」を作るのもおすすめです。
音読み・訓読みをストーリーで覚える方法
次に、音読みと訓読みを“ストーリー”にして覚えると記憶に残りやすくなります。
たとえば「悼」は「とう」と「いたむ」ですが、次のように関連づけられます。
『とう(悼)=人の死をいたむ(痛む)』とセットで覚えると、音と意味が結びついて忘れにくくなります。
また、熟語ごとに情景を思い浮かべるのも効果的です。
| 熟語 | ストーリー例 |
|---|---|
| 追悼(ついとう) | 亡くなった人を“追って”思い出す。 |
| 哀悼(あいとう) | 哀(かな)しみの心で“悼む”。 |
| 痛悼(つうとう) | 痛いほど悲しみを感じて“悼む”。 |
このように、意味の中に感情や情景をリンクさせることで、自然に覚えられるようになります。
漢字検定対策に使えるおすすめ勉強法
最後に、漢字検定を目指している学生に向けて、効果的な学習法を紹介します。
- 部首ごとにまとめた「意味別ノート」を作る。
- 漢字カードを使って読み・書き・意味を3秒で復唱する。
- 似た形の漢字(例:悼・陸)を並べて違いを確認する。
- 漢字アプリで音訓の発音を耳から覚える。
特に、「部首別ノート」はおすすめです。
同じグループで漢字を整理すると、試験中でも「この漢字はどんな意味だったか」がすぐに思い出せます。
漢字を単独で覚えるのではなく、関連づけて覚えることで、記憶が定着しやすくなります。
まとめ|「悼」は「りっしんべん」に卓。意味を知ると忘れない
ここまで、「こざとへんに卓」と書かれるように見える漢字「悼」について、読み方・意味・使い方を詳しく学んできました。
最後に、この記事のポイントを振り返りながら、学んだことを整理しましょう。
意味や部首を理解することで、漢字がぐっと身近な存在になります。
この記事のポイントおさらい
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 漢字 | 悼(とう/いたむ) |
| 部首 | りっしんべん(忄) |
| 意味 | 人の死を悲しむ・心をいためる |
| 成り立ち | 「りっしんべん」+「卓」で、心が高ぶり悲しむ様子を表す |
また、「こざとへん」と「りっしんべん」の違いを理解することで、形の似た漢字も見分けやすくなりました。
「悼」は心の動きを表す漢字なので、地形や場所を表す「こざとへん」とは意味の分野が異なります。
こざとへんとの違いを再確認
見た目が似ている「こざとへん(阝)」は、土地・坂・丘などを意味する部首でした。
たとえば、「附(ふ)」「阳(よう)」「阡(せん)」などはすべてこざとへんの仲間です。
「こざとへん=場所や地形」「りっしんべん=心や感情」と覚えると、迷わなくなります。
このように部首ごとに意味を整理すると、漢字の構造や成り立ちが自然に理解できるようになります。
次に覚えたい関連漢字の紹介
「悼」と一緒に学んでおくとよい漢字を、部首ごとにいくつか紹介します。
| 部首 | 関連漢字 | 意味の共通点 |
|---|---|---|
| りっしんべん | 情・悲・想・懐 | 心や感情を表す |
| こざとへん | 陸・防・院・附・阡 | 地形・場所を表す |
このように漢字をグループ化して覚えると、関連性が見えてきます。
漢字は「形」「音」「意味」の3つを同時に理解すると、忘れにくくなるというのが学習のコツです。
「悼」は中学校でも習う漢字なので、この機会にしっかり覚えておきましょう。

