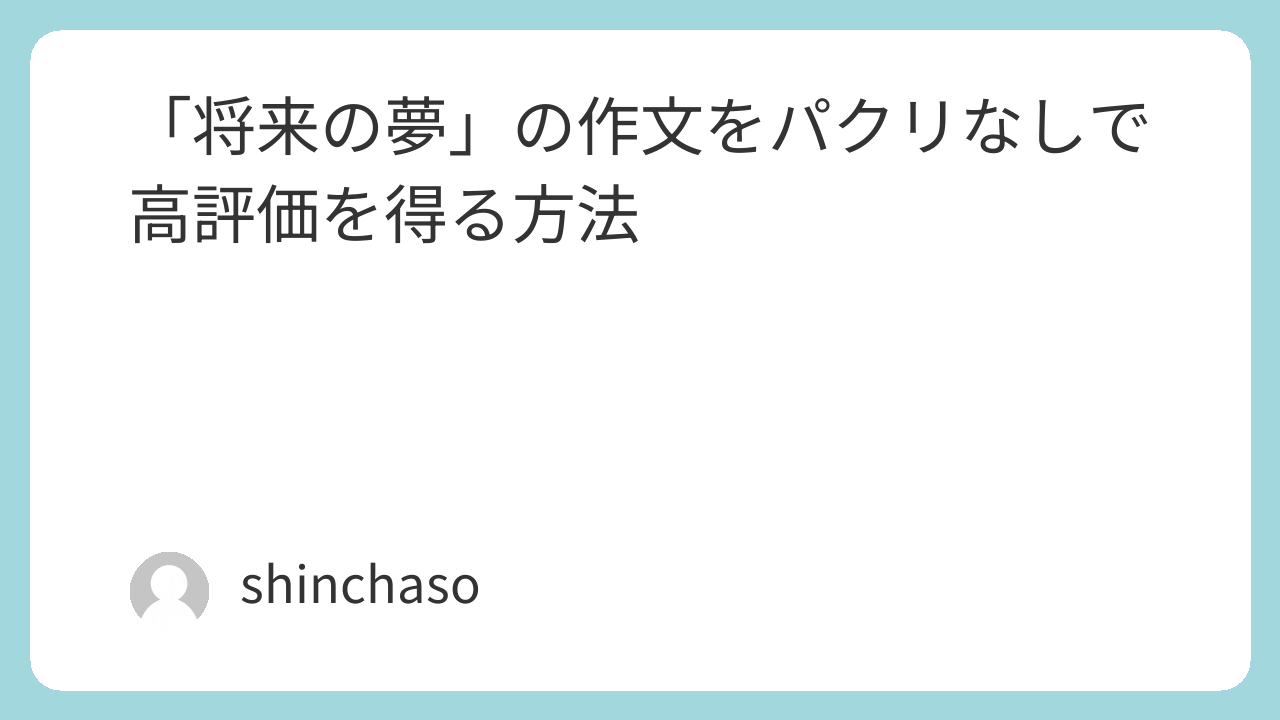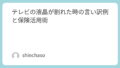「将来の夢」についての作文を書くとき、「何を書けばいいかわからない」「ネットの例文をそのまま使いたい」と悩む人も多いのではないでしょうか。しかし、パクリは信頼を損なうだけでなく、自分自身の成長のチャンスを逃すことにもつながります。
この記事では、パクリに頼らず、自分の言葉でオリジナルな作文を仕上げるための方法を詳しく解説します。誰でも実践できる具体的なテクニックや構成のコツを紹介しているので、作文が苦手な人でも安心して読み進められる内容になっています。
この記事でわかること:
-
パクリと参考の違い、そしてパクリがもたらす問題点
-
自己分析から夢を見つけるための具体的な方法
-
自分の体験や感情を使って作文にオリジナリティを出すコツ
-
読みやすく評価されやすい作文の構成と書き方の基本
将来の夢 作文 パクリを避けるための基本的な考え方
作文を書くとき、「他の人のを真似すれば楽に書けるのでは?」と考えてしまうこと、誰にでもあると思います。特に「将来の夢」というテーマは、自分の中にまだ明確なビジョンがないと書きづらく、他人の例文に頼りたくなる気持ちも自然です。
でも、作文はただ正解を書けばいいわけではなく、自分の思いや考えを文章にすることが目的です。たとえ完璧に見える文章でも、それが他人のコピーなら、自分自身の考えを表現する機会を失ってしまいます。
このセクションでは、「パクリ」と「参考」の違い、なぜ作文でのパクリが問題になるのか、そしてオリジナルの作文を書くためにまず大切にしたい心構えについてお話しします。
パクリと参考の違いとは何か?
「パクリ」と「参考」は、似ているようで意味が大きく異なります。作文に取り組むとき、多くの人がまず他人の例文を読んでイメージをつかもうとします。それ自体は決して悪いことではありません。むしろ、初心者にとってはとても良い勉強法です。ただし、その行動が「参考」ではなく「パクリ」になってしまうと、話は変わってきます。
「パクリ」とは、他人の書いた文章をそのまま、もしくは表現だけ少し変えて自分のものとして提出する行為です。これは、たとえ意図的でなくても他人のアイデアを盗用する行為とみなされます。特に、ネット上の例文や過去の作文集にある内容をそのまま使ってしまうと、著作権の問題や評価の低下につながることもあります。
一方、「参考にする」というのは、自分の考えを深めたり、構成や表現の仕方を学んだりするために、他人の文章をヒントにすることです。大切なのは、「読んだあとに必ず自分の経験や考えに置き換えること」。たとえば、誰かが「医者になりたい」という夢について書いていたとして、自分は医者に興味がなくても、「人の役に立ちたい」という部分に共感し、そこから福祉の道を考えるきっかけになったなら、それは立派な参考です。
このように、他人の文章から得た知識や気づきを、自分の視点で再構築し、自分の言葉で書き直すことが「参考」の本質です。「似ていても中身は全く別物」というのが理想ですね。
なぜ作文でパクリが問題視されるのか?
作文における「パクリ」は、多くの場面で問題視されます。その理由は主に3つあります。
まずひとつ目は、学びの機会を自分で失ってしまうことです。作文を書くという行為は、単なる文章作業ではありません。自分の頭で考え、自分の感情を整理し、言葉にして他者に伝えるという大切なプロセスです。この訓練は、将来レポートを書いたり、人前で発表したり、仕事で意見を述べたりする力に直結します。ところが、他人の文章をそのまま使ってしまえば、自分で考える機会を放棄してしまうのと同じ。結果的に「書く力」「考える力」「伝える力」が育たなくなります。
次に、評価する側からの信頼を失うというリスクがあります。先生や審査員は、何百、何千という作文を読んでいます。だからこそ、文章の構成や表現に違和感があれば、すぐに「これはどこかで読んだことがある」と気づかれてしまう可能性があります。仮にバレなかったとしても、「どこかで見たような文章だな」「本人の言葉じゃない気がする」と思われたら、それだけで評価は下がってしまいます。
最後に、著作権という法律的な問題もあります。他人の文章をそのまま使うことは、著作権侵害になることもあります。インターネット上の例文やコンクールの入賞作などは特に注意が必要で、無断で転載する行為は、法的にも倫理的にも問題です。
これらの理由から、作文でのパクリは絶対に避けるべきものとされているのです。
パクリを防ぐために大切な心構え
作文をパクリなしで書くために一番大切なのは、「うまく書く」ことではなく、「自分の言葉で正直に書く」という姿勢です。多くの人が作文を苦手に感じるのは、「完璧に書かなければいけない」というプレッシャーがあるから。でも、作文に完璧な正解はありません。
自分が感じたこと、考えたこと、体験したことを、素直に書く。それが、読み手に一番響く文章になります。難しい言葉を使おうとしなくて大丈夫です。むしろ、小さな出来事に対する自分の気持ちや気づきを丁寧に綴ることが、オリジナリティを高め、説得力のある作文につながります。
また、「書くことがない」と感じたときこそ、自分の過去や日常を振り返ってみてください。どんな些細なことでも構いません。たとえば、家で飼っているペットとの時間、学校で感動した出来事、テレビで見た誰かの姿に影響を受けた話など、すべてが作文のネタになります。
大事なのは、「それをどう感じたか」「自分にとってどんな意味があるか」を言葉にすることです。それができれば、パクリの必要は一切なくなります。
作文は、ただ評価されるために書くものではなく、自分自身を知るため、そして他人に伝えるための手段です。その心構えを持つことで、あなたの作文は自然とオリジナルになっていきます。
将来の夢 作文 パクリを回避するオリジナルな書き方(導入文)
「将来の夢」についての作文を書くとき、「何を書けばいいのか思いつかない」「うまく書ける気がしない」と感じる人は少なくありません。特に作文に苦手意識があると、「うまい文章に見える例文を少しだけ変えて使っちゃおうかな…」という誘惑に駆られることもあるでしょう。
でも、実はオリジナルな作文を作る方法は、難しくありません。少し視点を変えて、「自分の考え方や体験」を文章に落とし込む工夫をするだけで、自然と他人とは違う、自分だけの作文が生まれます。
このセクションでは、「パクリ」を避けながら、しっかりと評価される作文を書くための具体的な方法をご紹介します。大切なのは、自分の中にある想いや考えを上手に引き出すこと。誰でもできる3つのステップで、オリジナルな作文作りのコツを身につけましょう。
自己分析から始める夢の明確化
まず最初に行うべきことは、「自分の将来についてしっかりと考えること」です。将来の夢を作文に書くには、まずその夢が何なのかを明確にする必要があります。「将来の夢なんてまだ決まっていない…」という人も多いでしょうが、それはまったく問題ありません。大切なのは、「どんなことに興味があるか」「どんな生き方をしてみたいか」を見つめ直すことです。
自己分析の方法としておすすめなのは、次のような質問に自分で答えてみることです:
-
小さい頃、何に興味があった?
-
最近、時間を忘れて夢中になったことは?
-
尊敬する人はどんな人?その人のどんなところが好き?
-
将来、自分が誰かの役に立つとしたら、どんな方法で?
これらの質問に答えるうちに、「なんとなくこういうことが好きかも」「こんな方向が自分に合っているかも」といった気づきが生まれます。例えば、「子どものころから動物が好き」という人は、獣医や動物園の飼育員、ペットショップの店員など、さまざまな選択肢が考えられます。
また、自己分析には「SWOT分析」や「マインドマップ」を使うのも有効です。紙に思いついたことを自由に書き出すだけでも、自分の頭の中が整理されていきます。
このようにして、「自分はどんな人間なのか」「何に向いているのか」を知ることができれば、他人の夢を借りなくても、自分自身の言葉で作文が書けるようになります。
経験や感情を活かす作文テクニック
オリジナルな作文にするためには、単に「将来の夢は〇〇です」と書くだけではなく、「なぜその夢を持ったのか」「どう感じているのか」といった自分だけのエピソードや感情を盛り込むことがポイントです。
作文のなかで具体的な体験談を入れると、それだけで一気に文章に説得力が出ます。例えば、「将来は保育士になりたい」と書く場合、次のような違いがあります。
・例1(表面的な作文):「私は将来、子どもが好きなので保育士になりたいです。」
・例2(具体的で感情が伝わる作文):「私は小学校のころ、妹の面倒をよく見ていました。泣いているときに一緒に絵本を読んで笑ってくれたとき、『誰かの心を明るくできる仕事って素敵だな』と思いました。それ以来、保育士に憧れています。」
このように、たった一つの出来事でも、自分がどう感じたかを書き加えることで、文章が生きてきます。そして、それは他人の作文とは決して被ることのない「自分だけの話」になります。
また、失敗した体験や、悩んだ経験を書くのも効果的です。「一度は夢をあきらめそうになったけれど…」という展開は、読み手の心に残りやすく、真剣さが伝わります。
作文は「うまく見せること」が目的ではなく、「自分の思いを相手に伝えること」が本質です。その意味では、正解はひとつではなく、自分の本音をしっかりと表現することが最大のテクニックと言えるでしょう。
インスピレーションの得方とその活用方法
オリジナルな作文を書くために、「まったく何も見ずに一から考えよう」とすると、かえって難しく感じてしまうかもしれません。そんなときに活用したいのが、インスピレーションを得る方法です。
まずおすすめなのは、他人の作文やインタビュー記事、動画などを「観察」することです。たとえば、夢に向かって努力している人のドキュメンタリー番組や、YouTubeで職業紹介をしている動画を見てみると、「こんな仕事もあるのか」「自分もやってみたい」と思えるものに出会えるかもしれません。
また、家族や友人に「どんな仕事に向いていると思う?」と聞いてみるのもいい方法です。自分では気づかなかった意外な一面を発見できることがあります。
重要なのは、「見たり聞いたりした内容をそのまま書くのではなく、自分の中で一度咀嚼してから書くこと」です。たとえば、「お医者さんのインタビューを見て感動した」だけで終わらせず、「自分も人を助ける立場になりたい」「医療だけでなく福祉も視野に入れたい」など、自分なりの視点を加えると、そこにはしっかりとしたオリジナリティが生まれます。
インスピレーションは、無理にひねり出すものではありません。日々の生活の中にヒントはたくさん転がっています。何気ない会話や、本で読んだ一言が、作文のネタになることもあるのです。
将来の夢 作文 パクリにならない構成の工夫(導入文)
作文を「書くのが苦手」と感じる人の多くは、「どう構成すればいいか分からない」と悩んでいます。特に「将来の夢」というテーマは、書く内容も自由度が高く、逆にそれがハードルになってしまうこともあるでしょう。
そこで大事になるのが、構成の工夫です。作文には効果的な型があります。これを意識するだけで、文章全体が整い、読みやすく、かつ説得力のあるものになります。そして、しっかりとした構成を使えば、自分の体験や感情を自然に盛り込めるため、パクリにならないオリジナルな作文を作ることができるのです。
このセクションでは、基本構成の型、実際の作文例、そして文章を魅力的にするための表現のポイントについて詳しく解説していきます。構成のコツを押さえれば、誰でも「伝わる作文」が書けるようになりますよ。
序論・本論・結論の基本構成
作文を書くうえで最も効果的かつ基本的な構成が、「序論・本論・結論」の三部構成です。これはプレゼンテーションやスピーチなど、あらゆる文章表現に通じる「型」と言っても過言ではありません。作文も例外ではなく、この構成を使うことで、内容がスッと頭に入りやすくなります。
序論では、「何について書くか」を簡潔に述べましょう。「私の将来の夢は〇〇です。」というシンプルな一文から始めてもかまいません。大事なのは、読み手に「これからこのテーマについて書きます」と伝えることです。ここでインパクトを持たせるために、きっかけとなった出来事や印象的な一言を添えると、ぐっと文章が引き締まります。
本論では、「なぜその夢を持つようになったか」「どのような体験やきっかけがあったか」を中心に書いていきます。具体的な出来事や、そこから得た感情・学びを織り交ぜながら書くと、説得力が出てきます。ここが最もボリュームを出す部分になりますので、自分のエピソードを詳しく書いてみましょう。
結論では、「その夢に向けて今後どうしていきたいか」「どのような決意を持っているか」をまとめます。作文を読み終えたときに、読者が「この人は本気でその夢を追いかけようとしているんだな」と感じられるような締めくくりが理想です。
この三部構成を意識するだけで、作文は自然とまとまり、他人の真似をする必要がない、自分らしい文章が完成します。
よくある作文例と改善のポイント
インターネットや過去の作文集にある「将来の夢」の例文を読むと、内容が似通っているケースが多く見られます。例えば、「サッカー選手になりたい」「保育士になりたい」「医者になりたい」といったテーマはよく使われていますし、書き方も似てくる傾向にあります。
しかし、内容が被ってしまっても、**書き方次第でオリジナル性は十分に出せます。**以下によくある作文のパターンと、それを改善するためのポイントを紹介します。
●【よくある作文】
「私は将来、保育士になりたいです。子どもが好きだからです。子どもたちと遊んだり、お世話をしたりする仕事が楽しそうだと思います。だから保育士になりたいと思います。」
→【改善ポイント】
-
体験談の追加:「妹の世話をしたときに感じた達成感」や「保育園の先生の優しさに感動した出来事」など、感情が動いたエピソードを入れる。
-
理由の掘り下げ:「子どもが好きだから」というだけでなく、「子どもたちの成長をそばで支えたい」「安心して過ごせる空間を作りたい」といった自分なりの視点を入れる。
-
未来への展望:「どんな保育士になりたいか」「どのように努力していくか」などの決意を加える。
このように、構成や内容に少し手を加えるだけで、読み手の印象は大きく変わります。「ありふれた夢」でも、「自分の経験をどう重ねているか」が伝われば、他人の作文とはまったく違った作品になります。
読みやすく評価されやすい文章の特徴
どんなに良い内容でも、文章が読みにくければ評価は下がってしまいます。逆に、内容がシンプルでも「伝わりやすい文章」を意識するだけで、評価はぐっと高まります。
以下に、読みやすく、かつ高評価を得やすい作文の特徴を紹介します:
-
一文が短く、簡潔であること
→ 1文が長すぎると意味が伝わりにくくなります。「主語+述語」の基本を意識し、1文は40〜50文字以内を目安にしましょう。 -
「です・ます調」「である調」の統一
→ 文体がバラバラだと、読みにくくなります。特に「作文」では「です・ます調」が一般的ですので、最後まで一貫させるようにしましょう。 -
段落ごとに話題が変わる
→ 段落の最初の1文に要点を書くようにすれば、読み手が話の流れをつかみやすくなります。段落の切れ目は、読む人の集中を途切れさせないための大事な工夫です。 -
表現に気持ちが込められている
→ 難しい言葉を使わなくても、「嬉しかった」「悔しかった」「驚いた」といった素直な感情を入れるだけで、読み手の共感を得やすくなります。 -
誤字脱字や文法ミスがない
→ 基本的なことですが、文章の信頼性を保つためにも必ず確認をしましょう。読んだあとに少し時間を置いて見直すのがポイントです。
読みやすくて誠実な文章は、それだけで「この人は一生懸命考えて書いたんだな」と伝わります。結果的に、作文全体の評価を底上げしてくれる要素にもなります。
将来の夢 作文 パクリなしで高評価を得るためのまとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 作文の「パクリ」と「参考」は意味が異なる
- パクリは学習機会を奪い、評価を下げる原因になる
- 自己分析によって夢の方向性を見出すことが大切
- 体験談や感情を交えて書くとオリジナリティが高まる
- 他人の意見や動画からヒントを得ても、自分の言葉に置き換えることが重要
- 序論・本論・結論の構成を守ると説得力が増す
- 例文を見て終わらず、自分の経験に置き換えて表現する
- 読みやすい文は短く簡潔で、段落に分けて書くと効果的
- 素直な感情表現が読み手の共感を得やすくする
- 正しい文法・語尾の統一・誤字脱字のチェックは基本中の基本
作文は「正解のある課題」ではなく、「自分自身を表現する機会」です。うまく書こうとするよりも、自分の気持ちを素直に言葉にすることが、読者の心を動かす文章につながります。パクリに頼らず、自分の経験や考えに自信を持って、あなただけの作文を仕上げてください。